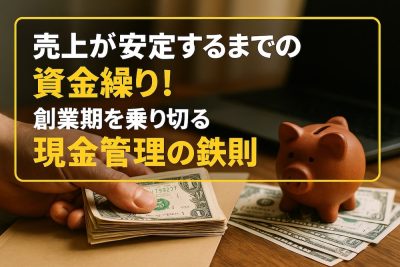「起業したいけれど、お金のことが心配で…」。
そんな声を、私はこれまで何度も耳にしてきました。
こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの河野真一です。
長年、証券会社でお金のプロとして働き、独立してからは多くの中小企業や個人事業主の方々の資金相談に乗ってきました。
その経験から痛感するのは、創業初期における「資金繰り」こそが、事業を継続できるかどうかの大きな分かれ道になるという現実です。
夢と希望を胸にスタートしたものの、日々の現金が底をつき、志半ばで諦めざるを得なかった起業家を、残念ながら何人も見てきました。
しかし、正しい知識と準備があれば、この創業期の荒波は必ず乗り越えられます。
この記事では、私が現場で見てきたリアルな事例を踏まえながら、創業期を乗り切るための「現金管理の鉄則」を具体的にお伝えします。
資金繰りの不安を解消し、あなたが思い描く事業を軌道に乗せるための一助となれば幸いです。
創業期における資金繰りの基本
起業して間もない時期の資金繰りは、航海に乗り出したばかりの小舟のようなものです。
穏やかな日もあれば、嵐に見舞われる日もあるでしょう。
まずは、その特性を理解することが重要です。
起業直後のキャッシュフローの特性とは
起業直後は、どうしても支出が先行しがちです。
商品やサービスが完成し、お客様に認知され、実際に売上が入金されるまでには、想像以上に時間がかかることも少なくありません。
一方で、家賃や仕入れ代金、人件費といった支払いは待ってくれません。
この「入ってくるお金よりも出ていくお金が早い」という状態が、創業初期のキャッシュフローの大きな特徴です。
「売上は立っているのに、なぜか手元にお金がない…」。
そんな状況に陥らないためにも、現金の流れを正確に把握し、コントロールすることが求められます。
売上ゼロでも必要な出費リスト
たとえ売上がまだ一本も立っていなくても、事業を運営していくためには様々な費用が発生します。
具体的にどのような出費があるのか、事前にリストアップしておくことが大切です。
- 法人設立関連費用: 定款認証手数料、登録免許税など(法人の場合)
- 事務所・店舗関連費: 敷金礼金、家賃、保証金、内装工事費
- 設備・備品費: パソコン、デスク、電話、専門機器など
- 仕入れ費: 商品の原材料費、商品仕入れ代金(小売業などの場合)
- 広告宣伝費: ホームページ作成費、チラシ・名刺作成費
- 水道光熱費・通信費: 電気、ガス、水道、インターネット回線、電話料金
- 人件費: 従業員給与(雇用する場合)、自身の生活費
- 諸経費: 交通費、消耗品費、会議費
- 税金・社会保険料: 法人税、所得税、消費税、健康保険料、年金保険料
これらの費用は、業種や事業規模によって異なります。
ご自身の事業計画に合わせて、具体的な金額を見積もっておきましょう。
起業家が陥りやすい「資金の落とし穴」
希望に満ちてスタートする起業ですが、資金面でつまずいてしまうケースも後を絶ちません。
ここでは、多くの起業家が陥りやすい「資金の落とし穴」をいくつかご紹介します。
1. 売上予測の甘さ
「これくらいは売れるだろう」という楽観的な見通しは禁物です。
市場調査を十分に行い、控えめな売上予測から資金計画を立てるようにしましょう。
2. 運転資金の見積もり不足
初期投資だけでなく、事業を継続していくための運転資金がどれくらい必要か、正確に把握できていないケースが散見されます。
最低でも3ヶ月分、できれば6ヶ月分の運転資金は確保しておきたいところです。
3. 過度な初期投資
最初から立派なオフィスを構えたり、高価な設備を導入したりと、見栄えにこだわりすぎるのは危険です。
スモールスタートを心がけ、事業の成長に合わせて段階的に投資していくのが賢明です。
4. 税金・社会保険料の準備不足
利益が出始めると、忘れた頃にやってくるのが税金の支払いです。
納税資金を別途確保しておかないと、いざという時に資金ショートを起こしかねません。
これらの落とし穴を事前に認識し、対策を講じておくことが、創業期を乗り切るための第一歩となります。
見落としがちな現金管理の盲点
帳簿上は順調に見えても、実は危険な状態に陥っていることがあります。
現金管理における見落としがちなポイントを理解し、健全な経営を目指しましょう。
黒字倒産はなぜ起こるのか
「利益が出ているのに倒産するなんて、あり得ないのでは?」
そう思われるかもしれません。
しかし、現実に「黒字倒産」という事態は起こり得るのです。
黒字倒産とは、損益計算書上では利益が計上されているにもかかわらず、支払いに必要なお金が手元になくなり、事業継続が不可能になる状態を指します。
なぜこのようなことが起こるのでしょうか。
主な原因は、売掛金の回収遅れや未回収、過剰な在庫、多額の設備投資などが挙げられます。
例えば、商品を掛けで販売し、売上は計上されたものの、その代金が入金されるのが数ヶ月先だとします。
その間にも、仕入れ代金や経費の支払いは発生します。
この入金と支払いのタイミングのズレが大きくなると、手元の現金が不足してしまうのです。
「利益は意見、キャッシュは事実」という言葉があります。
会計上の利益も重要ですが、それ以上に日々の現金の動きをしっかりと把握することが、企業経営においては生命線となるのです。
生活費と事業資金の線引き
特に個人事業主や設立間もない法人に多いのが、経営者個人の生活費と事業の資金が曖昧になってしまうケースです。
「ちょっと足りないから、会社の口座から引き出して生活費に…」といった安易な資金の移動は、後々大きな問題を引き起こす可能性があります。
生活費と事業資金を明確に分けるべき理由は、主に以下の2点です。
- 事業の正確な収支状況を把握するため:
資金が混同していると、事業が本当に利益を生んでいるのか、どれくらいの運転資金が必要なのかといった実態が見えにくくなります。 - 税務上の問題を避けるため:
税務調査が入った際に、事業と無関係な支出が経費として計上されていれば、追徴課税や加算税の対象となる可能性があります。
事業用の銀行口座と個人用の銀行口座は必ず分け、資金の移動には明確なルールを設けましょう。
経営者自身の給与(役員報酬)も、きちんと経費として計上し、そこから生活費を賄うのが原則です。
キャッシュフローと利益の違いを理解する
「利益がたくさん出ているから、資金繰りは大丈夫だろう」と考えるのは早計です。
会計上の「利益」と、実際に手元にある「現金(キャッシュフロー)」は、必ずしも一致しません。
利益とは:
一定期間の収益から費用を差し引いたもので、企業の経営成績を示します。
損益計算書で確認できます。
キャッシュフローとは:
一定期間における現金の収入と支出の差額で、現金の実際の増減を示します。
キャッシュフロー計算書で確認できます。
なぜ両者に違いが生まれるのでしょうか。
それは、会計上の収益・費用の計上タイミングと、実際の現金の入出金のタイミングが異なる場合があるからです。
また、減価償却費のように費用として計上されるが現金の支出を伴わないものや、借入金の返済のように現金の支出はあるが費用にはならないものも存在します。
| 項目 | 利益への影響 | キャッシュフローへの影響 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 売掛金の発生 | 収益として計上 | 影響なし(未入金) | 入金時にキャッシュイン |
| 買掛金の発生 | 費用として計上 | 影響なし(未払い) | 支払い時にキャッシュアウト |
| 減価償却費 | 費用として計上 | 影響なし | 現金の支出は設備購入時に発生済み |
| 借入金の返済 | 影響なし | キャッシュアウト | 元本返済部分は費用ではない |
| 在庫の増加 | 影響なし | キャッシュアウト | 仕入れ時に現金支出 |
このように、利益とキャッシュフローは別物であることを理解し、損益計算書だけでなく、資金繰り表やキャッシュフロー計算書も活用して、現金の動きをしっかりと管理することが不可欠です。
安定収益までの現金戦略
創業期を乗り越え、事業を安定軌道に乗せるためには、戦略的な現金管理が欠かせません。
ここでは、具体的な戦略について見ていきましょう。
最低限必要な「運転資金」の算出方法
運転資金とは、事業を日々運営していくために必要なお金のことです。
仕入れ、経費の支払い、給与の支払いなど、売上が入金されるまでの間に立て替えておくべき資金と言えます。
この運転資金が不足すると、いわゆる「資金ショート」に陥り、黒字であっても倒産してしまう可能性があります。
では、自社にとって最低限必要な運転資金はどのように算出すればよいのでしょうか。
一つの目安として、「経常運転資金」という考え方があります。
これは、以下の計算式で求められます。
経常運転資金 = 売上債権(売掛金+受取手形) + 棚卸資産(在庫) - 仕入債務(買掛金+支払手形)
簡単に言えば、「まだ回収できていない売上」と「まだ売れていない在庫」の合計から、「まだ支払っていない仕入れ代金」を差し引いた金額です。
この金額がプラスであれば、その分だけ運転資金が必要になるということです。
もう一つの簡単な目安としては、「固定費の数ヶ月分」を準備しておくという方法です。
一般的には、最低でも3ヶ月分、できれば6ヶ月分の固定費(家賃、人件費、リース料など、売上に関わらず毎月発生する費用)に相当する現金を常に手元に置いておくことが推奨されます。
これらの計算方法はあくまで目安です。
業種や事業規模、取引条件などによって必要な運転資金は大きく変動します。
自社の状況をしっかりと分析し、余裕を持った資金計画を立てることが肝心です。
3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月のシナリオ別現金管理
資金繰り計画は、一度作ったら終わりではありません。
事業の状況は刻々と変化するため、定期的に見直し、将来の現金の動きを予測することが重要です。
短期(3ヶ月)、中期(6ヶ月)、長期(12ヶ月)といった期間別に、複数のシナリオを想定して現金管理を行うことをお勧めします。
シナリオ1:3ヶ月計画(短期)
- 目的: 直近の資金ショートを防ぐ。
- 内容:
- 日々の現金の入出金を正確に把握し、資金繰り表を作成する。
- 売掛金の回収予定日と買掛金の支払予定日を厳密に管理する。
- 短期的な資金不足が見込まれる場合は、早めに資金調達策(短期借入など)を検討する。
- ポイント: 精度の高い予測が求められます。
シナリオ2:6ヶ月計画(中期)
- 目的: 季節変動や一時的な業績悪化に対応する。
- 内容:
- 過去のデータや市場動向を分析し、中期的な売上や費用の変動を予測する。
- 設備投資や新規採用など、中期的な支出計画を織り込む。
- 複数の売上パターン(楽観、標準、悲観)を想定し、それぞれの資金繰りをシミュレーションする。
- ポイント: 柔軟性と備えが重要になります。
シナリオ3:12ヶ月計画(長期)
- 目的: 事業拡大や新規事業への投資判断を行う。
- 内容:
- 長期的な事業戦略に基づき、必要な資金額と調達方法を計画する。
- 市場環境の変化や競合の動向などを踏まえ、将来のリスクと機会を評価する。
- 安定的なキャッシュフローを生み出すための収益構造改革を検討する。
- ポイント: 将来を見据えた戦略的な視点が不可欠です。
これらの計画を定期的に更新し、実績と比較することで、資金管理の精度を高めていくことができます。
コスト削減と投資判断のバランス
創業期においては、限られた資金を有効に活用するために、コスト削減は常に意識すべき課題です。
しかし、単に支出を切り詰めるだけでは、事業の成長を妨げてしまう可能性もあります。
大切なのは、「削減すべきコスト」と「投資すべきコスト」を見極め、そのバランスを取ることです。
削減すべきコストの例
- 固定費の見直し:
- オフィスの賃料(より安価な場所への移転、シェアオフィスの活用など)
- 通信費、水道光熱費(プランの見直し、節約の徹底)
- 不要なサブスクリプションサービスの解約
- 変動費の抑制:
- 仕入れコストの交渉
- 外注費の見直し(内製化できる業務はないか検討)
- 旅費交通費の削減(オンライン会議の活用など)
投資すべきコストの例
- 人材育成・採用: 事業成長の核となる優秀な人材への投資
- マーケティング・広告宣伝: 新規顧客獲得やブランド認知度向上への投資
- 研究開発: 新しい商品やサービスの開発、既存事業の改善への投資
- 設備投資: 生産性向上や業務効率化に繋がる設備への投資
若手起業家の体験談:判断ミスが命取りに
以前、私が相談に乗った若手起業家のAさんは、デザイン性の高いオフィスにこだわり、初期費用と毎月の家賃が高額になっていました。
「お客様からの見栄えも大切だから」というのがAさんの言い分でした。
しかし、開業から半年経っても売上は伸び悩み、あっという間に運転資金が底をつきそうになりました。
慌ててコスト削減に着手しましたが、時すでに遅し。
結局、事業の立て直しは難しく、撤退を余儀なくされました。
Aさんのケースは、まさにコスト削減と投資判断のバランスを見誤った典型例です。
もちろん、事業内容によっては初期投資が重要な場合もあります。
しかし、「何のためにそのコストをかけるのか」「それによって将来どのようなリターンが見込めるのか」を冷静に判断することが、起業家には求められます。
「今は我慢の時」と耐え忍ぶべきか、「ここは勝負どころ」とアクセルを踏むべきか。
その見極めが、創業期の資金繰りを成功させるための鍵となるのです。
信頼を得る資金調達とそのタイミング
事業を成長させるためには、どこかのタイミングで外部からの資金調達が必要になることもあります。
しかし、やみくもに借り入れをすれば良いというわけではありません。
信頼を得られる資金調達とは何か、そしてその適切なタイミングについて考えてみましょう。
自己資金と外部資金の使い分け
資金調達の方法は、大きく分けて「自己資金」と「外部資金」の2つがあります。
- 自己資金:
経営者自身や家族、親族などから調達する資金です。
返済の必要がない、あるいは返済条件が緩やかであることが多く、経営の自由度が高いのがメリットです。
一方で、調達できる金額には限りがあります。 - 外部資金:
金融機関からの融資、投資家からの出資、補助金・助成金などがこれにあたります。
自己資金だけでは賄えない大きな金額を調達できる可能性がありますが、返済義務が生じたり(融資)、経営に関与されたりする(出資)ことがあります。
創業初期は、まず自己資金で事業をスタートし、実績を積みながら外部資金の活用を検討するのが一般的です。
事業計画や成長ステージに合わせて、これらの資金をどのように組み合わせるかが重要になります。
例えば、事業の立ち上げ費用や初期の運転資金は自己資金で賄い、事業が軌道に乗り始め、さらなる拡大を目指す段階で金融機関からの融資を検討するといった具合です。
補助金・融資・親族援助…現実的な選択肢
外部からの資金調達には、いくつかの選択肢があります。
それぞれの特徴を理解し、自社に合った方法を選びましょう。
1. 補助金・助成金
国や地方自治体が、特定の目的(創業支援、研究開発、雇用促進など)のために支給する資金です。
原則として返済不要なのが最大のメリットですが、公募期間が限られていたり、申請手続きが煩雑だったりする場合があります。
また、採択されるまで時間がかかることも考慮に入れる必要があります。
2. 融資
金融機関(日本政策金融公庫、信用金庫、銀行など)から事業資金を借り入れる方法です。
創業期には、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」などが比較的利用しやすいでしょう。
融資を受けるためには、事業計画の妥当性や返済能力などが審査されます。
当然ながら返済義務があり、利息も発生します。
3. 親族・知人からの援助(借入・出資)
比較的柔軟な条件で資金を調達できる可能性があります。
しかし、金銭の貸し借りは人間関係に影響を及ぼすリスクも伴います。
たとえ親しい間柄であっても、借用書を作成するなど、条件を明確にしておくことがトラブル防止のために重要です。
金融機関との向き合い方:元証券マンの視点から
私が証券会社に勤務していた頃、多くの企業の資金調達に関わってきました。
その経験から言えるのは、金融機関は単にお金を貸すだけでなく、事業の成長を支援するパートナーにもなり得るということです。
金融機関と良好な関係を築くためには、以下の点が重要です。
- 誠実な情報開示:
事業の状況が良い時も悪い時も、正直に伝えることが信頼関係の基本です。
試算表や資金繰り表などの資料を定期的に提出し、経営状況を理解してもらう努力をしましょう。 - 明確な事業計画:
「なぜ資金が必要なのか」「調達した資金をどのように活用し、どのように返済していくのか」を具体的に説明できる事業計画が必要です。
夢を語るだけでなく、実現可能性の高い計画を示すことが求められます。 - 早めの相談:
資金繰りが厳しくなってから駆け込むのではなく、余裕があるうちから相談しておくことが大切です。
日頃からコミュニケーションを取っておけば、いざという時にスムーズに支援を受けられる可能性が高まります。
金融機関の担当者も、あなたの事業の成功を願っています。
数字だけでなく、あなたの事業にかける情熱やビジョンをしっかりと伝えることも、信頼を得るためには不可欠です。
メンタルと資金繰り:経営者の心を保つコツ
資金繰りの問題は、経営者の精神面に大きな影響を与えます。
お金の不安は、夜も眠れなくなるほどのストレスになることも少なくありません。
しかし、経営者が倒れてしまっては、元も子もありません。
不安とどう向き合うか
「来月の支払いは大丈夫だろうか…」
「もし売上が計画通りにいかなかったら…」
創業期の経営者は、常にこのような不安と隣り合わせです。
不安を感じること自体は、決して悪いことではありません。
それは、あなたが真剣に事業に向き合っている証拠でもあります。
大切なのは、その不安に飲み込まれず、適切に対処することです。
不安を軽減するためのヒント
- 現状を客観的に把握する:
まずは、資金繰り表などを使って、現金の状況を正確に把握しましょう。
漠然とした不安ではなく、具体的な課題が見えてくれば、対策も立てやすくなります。 - 信頼できる人に相談する:
一人で抱え込まず、家族、友人、先輩経営者、専門家(税理士や中小企業診断士など)に相談してみましょう。
話を聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になることがあります。 - 小さな成功体験を積み重ねる:
日々の業務の中で、目標を達成したり、問題を解決したりといった小さな成功体験を意識的に積み重ねることで、自信を取り戻し、前向きな気持ちを維持しやすくなります。
資金繰りと経営判断の「孤独」
「最終的な判断は、すべて自分一人で下さなければならない」。
経営者は、このような孤独を感じることが少なくありません。
特に資金繰りのような重要な問題に直面した時、そのプレッシャーは計り知れないものがあります。
しかし、あなたは決して一人ではありません。
周囲には、あなたを支えてくれる人が必ずいます。
1. 専門家の活用
税理士や公認会計士、中小企業診断士といった専門家は、資金繰りに関する的確なアドバイスをしてくれます。
客観的な意見を聞くことで、冷静な判断ができるようになるでしょう。
2. 経営者仲間との交流
同じように苦労や悩みを抱える経営者仲間との交流は、貴重な情報交換の場であると同時に、精神的な支えにもなります。
互いに励まし合い、知恵を出し合うことで、困難を乗り越える力が湧いてくるはずです。
3. 相談窓口の利用
商工会議所や自治体の産業振興課などでは、起業家向けの相談窓口を設けている場合があります。
公的な支援制度の情報を得られることもありますので、積極的に活用してみましょう。
孤独を感じた時は、遠慮なく周囲に助けを求める勇気も必要です。
「自然体で生きる」ための心の余白づくり
私のモットーは「自然体で生きる」ということです。
これは、起業家にとっても非常に大切なことだと考えています。
資金繰りのプレッシャーで心が張り詰めていると、良いアイデアも浮かびませんし、正しい経営判断も難しくなります。
心に「余白」をつくるためには、意識的に休息を取り、リフレッシュする時間を持つことが重要です。
私自身、長野の自然の中を山歩きしたり、地元のクラフトビールを楽しんだりする時間が、何よりのリフレッシュになっています。
頭を空っぽにして自然の中に身を置くと、不思議と新しい視点が見えてきたり、凝り固まっていた思考がほぐれたりするものです。
趣味に没頭する時間、家族と過ごす時間、あるいは何もしないでボーっとする時間。
どんな形でも構いません。
仕事から意識的に離れ、心と体を休ませる時間を作りましょう。
健全な心身があってこそ、困難な状況にも立ち向かっていけるのです。
資金繰りという現実的な課題と向き合いつつも、心の健康を保つことを忘れないでください。
まとめ
創業期の資金繰りは、確かに険しい道のりかもしれません。
しかし、正しい知識を身につけ、計画的に準備し、そして何よりも諦めない心があれば、必ず乗り越えることができます。
創業期の資金繰りで押さえるべき核心ポイント
改めて、この記事でお伝えした重要なポイントを振り返ってみましょう。
- キャッシュフローの重要性を理解する: 利益だけでなく、現金の流れを常に意識する。
- 運転資金を確保する: 最低でも3ヶ月分の固定費を目安に、余裕を持った資金計画を立てる。
- 計画と実績の管理を徹底する: 資金繰り表を活用し、定期的に見直しを行う。
- コスト意識を持つ: 削減すべきコストと投資すべきコストを見極める。
- 信頼できる相談相手を持つ: 一人で抱え込まず、専門家や仲間を頼る。
- 心の健康を保つ: 適度な休息とリフレッシュを忘れずに。
河野真一が伝えたい「乗り切る力」とは
私がこれまで多くの起業家の方々とお付き合いする中で感じてきたのは、最終的に事業を軌道に乗せることができる人に共通しているのは、困難な状況でも前を向き、学び続け、行動し続ける「乗り切る力」だということです。
資金繰りの問題は、決して避けては通れない壁です。
しかし、その壁を乗り越えるたびに、あなたは経営者としてより強く、賢くなっていくはずです。
その経験こそが、あなたの事業を成長させる最大の原動力となるでしょう。
読者へのエール:「あなたにも乗り越えられる」
今、資金繰りの不安を抱え、この先どうなるのだろうと悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、思い出してください。
あなたが起業を決意した時の熱い想いを。
実現したい夢や、社会に貢献したいという志を。
その情熱があれば、どんな困難も乗り越えられるはずです。
この記事が、あなたの「乗り切る力」を少しでも後押しできたなら、これ以上の喜びはありません。
あなたの挑戦を、心から応援しています。
頑張ってください!